「そんなのおかしいよ」
「なんで怒らないの?」
友達が口を揃えてそう言うたび、私は少し困った顔をして笑うしかなかった。
だって、本当に怒ってはいなくて。
その“怒り”と呼ばれる感情が、自分の中に見つからなかったのだ。
夫とマンションで暮らしていた10年間、私はずっとモヤモヤしていた。
言葉にするのは難しいけれど、空気がよどんでいた。
晴れない曇り空の下で、毎日を過ごしていたような感覚が、当たり前になっていた。
夫が息子と私を置いて、家を出ていってからも、彼のことを思い出すと、強い不安に襲われた。
身体の奥で何かが震え出すような、重たいものが胸を押しつぶすような——そんな感覚。
だから、なるべく考えないようにしていた。
できるだけ、思い出さないようにしていた。
夫がいないから不安なのではなく、このままで終わらせてはくれないだろうなという予感だ。
言いようのない不安として、日常を霧のように覆っていた。
出て行ってから数年がたった頃、夫から突然お金を請求された。
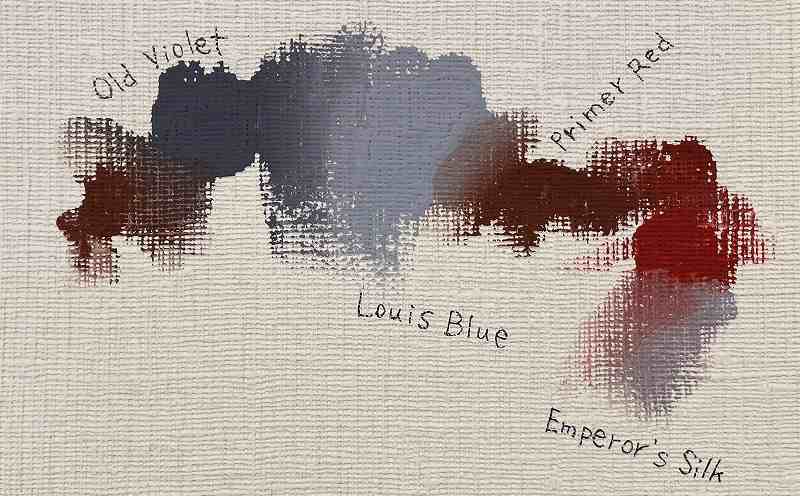
「やっぱり」と思った。
いつか言い出すと思っていた。
「怖いから払うしかない」
反射的にというより、元々そう言われたら最悪だと思っていたから、想定内のような気持ちで。
もう、心が不安の伏線回収をして、先回りしていた。
その“従おうとする私”に、友達は毎日のように怒ってくれた。
「目を覚ませ」と叱った。
それでも言われるがままで生きている私に呆れて、絶交寸前にまでなって——やっと私は慌てた。
そしてようやく、弁護士に相談する決心をした。
現実的に、支払える額ではなかったから。
やっと、理屈が感情を追い越してくれた。
普通は、こんなこと、無縁で済むものだと思っていた。
私自身も、そう願っていた。
でも弁護士に「どうしたいですか?」と聞かれたとき、
自分には“どうしたいか”がないことに気づいて、はっとした。
私は、ずっと怖かった。
ずっと、心に蓋をしていた。
ただ、それだけだった。
だから、どうしたいかを考えることができなかった。
いや?どうしたいか考えないから、こんな事になった??
離婚調停は約1年。
何度も席に着いたけれど、結局、不成立。
そこで私は知ったのだ。
人を介しても、話が通じない相手だったのだ、という現実を。
そうして私の中の「怖さ」は、形を持ち始めた。
感情が、解像度を上げて現れてきた。
ぼんやりしていた影が、輪郭を持って、はっきりと見え始めた。
それは、つまり——もっと怖くなる、ということだった。
何が怖いのかがわかるほどに、怖さが増していった。
耐えていたわけじゃなくて、逃げていただけだったんだ。
でも同時に、ようやく私は思い始めていた。
——ああ、私は、酷いことをされていたんだな、と。
——これは、怒ってもいいことだったんだな、と。
怒りは突然ではなかった。
感情は、静かに、じわじわと、湧いてきた。
まるで、冬の大地が春の陽射しで少しずつ溶けていくように。
私はようやく、「感じる」ことを、始めていた。
感じてから考えたのではなくて
相当考えた、自分のことに向き合う時間を使って、しっかりと思考したその後に、やっと感じるがやってきたのだった。
そういうこともあるってことだ。











