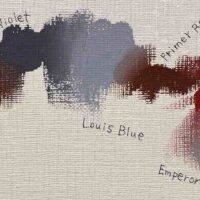アダルトチルドレンとは、子供の頃に機能不全家族で育ち、その経験が大人になってからの生きづらさにつながっているらしく、多分自分もそんな匂いがぷんぷんしているし、そういう大人にたくさん出会った。8割くらいそうだと聞いたこともある。
親からの期待に応えようと無理をしてきたような子供時代を送ると、成人後も「本当の自分」を見失いがちになる。
それを大人になってから自分で理解するのは難しいため、多くの人は専門家の助けを借りることを勧められる。この流れには、もがいた大人の大半がたどり着けると思う。しかしそこからが難しいのだ。
育った環境や体験は一人ひとり違っていて、しかも本人が昔のことを流暢に説明できるなんてことは少ない。だって現状がもう、拗れてるんだから。カウンセラーもその状況を知識と経験、想像で補いながら接する。現状の不具合がどういう仕組みで発動しているのか、相談者もカウンセラーも共に手探りしている状態。
更に、インナーチャイルドを強引に見つけ出そうとすると、防衛機制の中に閉じこもってしまい、かえって見つけることができなくなるとも言われる。
見つけたところで、「ふんっ」ってなっているチャイルド君。
そうなると、心の奥にいる“見失った自分”を探す作業は、長期戦覚悟。
覚悟を決めて、それなりのまとまった時間をつくって、お金をかけて、向き合い続ける必要がある。めちゃくちゃ難易度が高いじゃないか。
だから私はここは「触らない」という選択をとって諦めていた。
防衛機制もすごいことになっている実感がある。
タイムスリップでもしない限り無理だろうね。
ただ、皮肉なことに自分は、50歳を過ぎた今になって、その、タイムスマシンに強制的に乗らされることになった。

母は、認知症というわけではない。ただ、八十五歳になった身体は、目に見えて弱ってきた。
五年前の夏だったと思う。突然「もう一人では暮らせないから」と、母は私のマンションに転がり込んできた。
以前夫に「介護は俺はできないから頑張れよ」と言われていたことと、一人っ子で、どこかで親の面倒は自分が見るものだと思い込んでいた私が導き出した答えは「まあ、仕方ないな」と受け入れる一択だった。
当時、私の夫は家出して数年間別居している状態だったので、母と同居するかどうか、私の判断で決めることができてしまった。
それに、そんなに長い期間の同居と思っていなかった。母は脳腫瘍と診断されていた。素人でもわかるくらいの黒い影が検査ごとに大きくなっていた。あっという間に、下着が自分で履けなくなり、表情も消えた。高次脳機能障害のような症状も「脳腫瘍なら、そうなるよね」と納得していた。お迎えがくるまで、そう長くないのだ。
介護認定の手続きを進め、頭蓋骨に穴を開けて腫瘍の一部をとり、種類を見極めるための検査のための手術の予約をした。画像を見る限り、脳腫瘍の広がりは止まらず、もう母との時間は1か月くらいかもな、と思っていた。
ところが、手術の前日に主治医が「手術の必要はない」と言い出した。何をいってるのか意味が分からない。手遅れってことじゃなくて??
それは多発性硬化症による一時的な脳機能の低下であり、炎症は徐々に収まると言うのだ。手術は取り止めになり、母はそのままリハビリすることになった。
手術なしで、母は目に見えて元気になり、先生に褒められながら意気揚々と退院した。介護認定も外れた。嘘のような一か月だった。
ただ、それからが本当の始まりだった。
母は介護認定が外れた翌日から、突然「足が痛い」と言い出した。徐々に「動けない」「動かない」と、何かにつけて“助け”を求めてくるようになった。当時はそれが、母の癖だと気づいていなかった。週に3回接骨院に通い、月に一回くらいの頻度で仕事中の私に呼び出しがかかるようになる。
道端で突然動けないと騒いで、誰かが肩を貸すと自分の身体をぴんと伸ばして動かなくなり、数人に担がれて帰ってくるようになった。救急車や警察にお世話になることも増えた。そしてその都度、私が引き取りに行かなければならなかった。そして、母にお世話になった方々にお礼を言ってくるように言われて「申し訳ありませんでした」と菓子折りをもって挨拶に行き、いつも頭を下げていた。
そして、家の中でも、夜中に自分でトイレに行けないといって何度も起こされるようになった。私の身がもたないと思ってオムツを履かせたが、大人用のそれが一晩もたず、ベットに溢れさせていた。一晩中「たすけてください」「おこしてください」とロボットのように繰り返して叫び続けていた。
か細い声で、私が起きる行くまで、何時間も呼び続けている。幽霊が出たらこんな感じだろうな、という声だった。
おかしいな?とは思っていた。
小柄な母が、何でⅯサイズのオムツが一晩もたないのか?一体、身体のどこが悪くなって動かないのか?
また難病が再発して、脳に炎症がおきた?と調べてもらっても、特に脳に問題はなく、年齢的なものではないかということだった。
私はモヤモヤした。
そんな時、息子に、おばあちゃんは多分自分でできると思うよ、と言われる。
まさか…と思ったが、自分自身の生活に限界が来ていた。もうどうにでもなれと思い、夜中こっそり確認してみた。
母はわざわざ私の寝室のドアを開けて、ベットに一度戻ってから「起こしてください~」「手を貸してください~」と唱えていた。
次の日、母の叫びを無視して、私の部屋の内開きのドアは、母の力では開かないように荷物を置いて寝るようにした。すると、すんなり、夜中には自分でトイレに行くようになった。
それ以来、母はオムツを履いているが、トイレには自分で行っている。
母は、オムツを履いたらすぐにできた。経験者に聞くところによると、大人はオムツを履いても、普通は中に用を足すことができないらしい。
だからつまりそれは、そういう事なのだ。
母は、意図的に漏らして、手が動かなくなって、歩けなくなって、起き上がれなくなっている。
よく考えて、そういった真に迫った演技を本気でしているのだ。
多分、認知症ではない。。。
認知症ならよかったのに。
でも、この事から、母が私に、どういう風に接してきたのかが理解できるようになった。
毎日大人の私が、もう一度子供の頃の体験をなぞっているような状態なのだ。
今朝もそうだった。
デイサービスへ行く準備で薬の用意を頼むと、「できない」と母。
「朝飲む薬は何個?」と聞くと、「1個」と答える。
「じゃあ、ベッドの上にある薬は?」
「それは朝の薬」
「じゃあ3個あるから、朝は3個なのね?」
「そう、3個」
もう、わけがわからない。
周囲は「それ、認知症の初期じゃない?」と言う。でも私は、ずっと母とやり取りしてきた身として、少し違う気がしている。母は、自分の言葉通りに私が動かないと不安になる。だから“命令”のかたちを取って、なんとかコントロールしようとしている気がしてならない。
だって、デイサービスでは「全部自分でできます!すごいです!」と褒められているのだ。なのに、帰ってくるとベッドに仰向けになって「あーーーあーーーー」と叫ぶ。
仕事に出かけるふりをして、昼にそっと帰ってみたら、母は普通にテレビを見ていた。
こういうとき思ってしまう。この状態は、介護の問題というより、何か別の心の病なのではないか。専門の医療機関に相談すべきなんじゃないか。
――そうしないと、私の心のほうが壊れてしまいそうで。
中学三年の息子は冷静で、こう言ってくれる。
「ママの言うことは聞かないけど、俺の言うことは聞くから。俺が言うよ」
母が「できない」と大騒ぎしても、彼は冷たく、「できるでしょ」と言って放っておける。でも、私はどうしても、その間ソワソワしてしまう。
心の中で、「本当はできるんでしょ?」と思いながらも、放っておくことができないのだ。
その度に、私は小さな子供の自分と話し合うことができる。
母のわがままを前に、どう思って、どうしたくて、何が嫌なのかを言語化する作業。現在は「息子の言う通り!あたしも無視したい!」と言ってくる。
当時の気持ちをその人に代わって言語化していく作業を「感情の明確化」と言うらしいけれど、それを日常で繰りかけしているようなものだ。
この日々は、母の弱りゆく身体との闘いではなく、母と私――娘と母という関係の、何十年分の重なりのなかでもがく、言葉にならない闘いのようなものだ。
他人が見たらきっと、母がかわいそうに見えるだろう。
でも、今の私にとっては、幼い頃の私ができなかった「自分の味方をしてあげる」ということができる、最後のチャンスなのだと思う。
他の人がどう思うとしても、私が救われる、最後のチャンスなんだ。